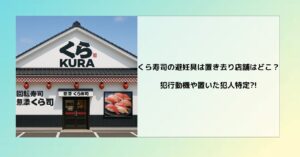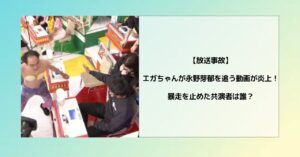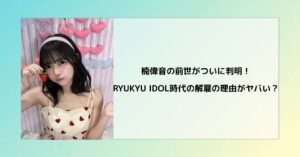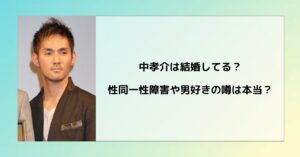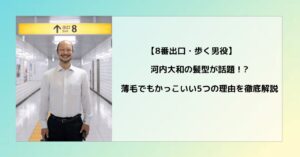2025年3月のVポイント×SMBCレディスで起きた、笠りつ子選手の「誤所からのプレー」によるルール違反が話題となっています。
ゴルフ規則14.7に基づく2打罰の内容から、選手自身のコメント、そして今後の競技におけるルール意識の重要性まで、徹底的に解説しています。
さらに、話題となった映像やネット上の反応、そしてゴルフ界に与えた影響についても詳しく紹介していきます。
視聴者の指摘はデマ!?笠りつ子のルール違反とは?

笠りつ子のルール違反で順位が変動!その全貌を解説します。
①“視聴者の指摘”はデマ?

今回のルール違反が明るみに出たのは、なんと視聴者からの指摘がきっかけと当初はされていました。
Xでも、
「あれ、今のドロップ、最初のやつ正しかったんじゃないか…?」
(引用:X)
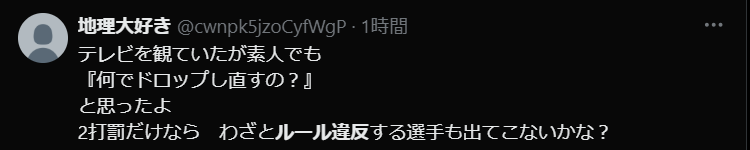
Vポイント×SMBCレディスの中継を見ていたファンが、SNS(旧Twitter)上で「笠選手のドロップがおかしいのでは?」などの投稿がありました。
この投稿が大きく拡散され、多くの視聴者が再確認する中で、疑念が強まり、最終的にJLPGA(日本女子プロゴルフ協会)が調査に乗り出したんです。
当初は視聴者から指摘があったとし、競技委員が最終ラウンド後に本人に確認して「誤所からのプレー」と認定。
しかし、3月24日JLPGAが一部訂正を発表しました。
24日に「視聴者からの指摘」ではなく「大会関係者からの指摘」であったことを明かし「訂正してお詫び申し上げます」と陳謝した。
(引用:Yahoo!ニュース)
そのため、視聴者からの指摘ではなく大会関係者からの指摘で判明したことになります。

しかし今の時代、スマホ1つで誰もが“目撃者”であり、“審判”になりうるということ。
古くからのゴルフファンなら、この誤所プレーやルール違反を見逃していません。
これはまさに、スポーツと観客の関係性が大きく変わってきた象徴とも言えますね。
試合会場だけでなく、視聴者の声がルールの適用にまで影響する時代。
まさに、今を生きる選手たちは「常に見られている」中でプレーしているんですね。
②ペナルティが適用されたのは何のプレー?


問題となったのは、大会2日目、13番ホール(パー4)での救済処置の場面でした。
笠選手は、レッドペナルティーエリアからの救済を選択。
通常、救済では2回のドロップを行い、規則に従ってプレーを続行します。
しかし今回のケースでは、
この2回目のドロップでプレーを続けたことが「誤所からのプレー」と見なされたわけです。
その結果、笠選手には2打罰が科され、スコアに大きな影響が出ました。
実際、7位で終える予定だった順位は13位へ後退。
たった2打とはいえ、シビアなプロの世界では致命的な差ですよね。
③ゴルフ規則14.7「誤所からのプレー」の意味


今回、適用されたルールは「ゴルフ規則14.7」。
このルールは「誤所からのプレー」に関するもので、指定された救済エリア外や、規定と異なる方法でプレーした場合に違反とされます。
救済エリア内でドロップしたボールが規定どおりに止まった場合、それが自動的に“インプレー”扱い。
ゴルフ競技におけるインプレーとは、プレイヤーがティーグラウンドからティーショットを打ち、その球がグリーン上に設置されたカップにインするまでの一連のプレーを指します。インプレー中は、ボールをあるがままの状態に保ってプレイすることが基本ですが、ローカルルールでは打ち難い時にボールを動かすことを許可していたり、正式なルールでも救済を受けたりするシチュエーションがあります。
(引用:じゃらんゴルフ)
したがって、それ以外の場所からプレーすれば誤所扱いになります。
特にペナルティーエリアからの救済は複雑で、プレーヤー自身が判断ミスを起こしやすいポイント。
選手側の理解不足だけでなく、その場の緊張感や時間制限なども重なるため、かなり神経を使う場面でもあるんですよね。
笠選手も「自分の判断ミス」と認めていますが、まさにゴルフが“頭脳のスポーツ”と言われるゆえんかもしれません。
知識と冷静さが問われる場面、そして痛恨の判断ミスが明暗を分けました。
④競技委員の判断と2打罰の根拠


中継を通して広がったSNSの指摘を受け、最終日終了後、JLPGAが調査を開始。
この判断により、「誤所からのプレー」とされ、2打罰が追加されることに。
これがなければ、最終スコアは「通算1アンダー」で7位タイ。
しかし罰則により、「通算1オーバー」となり、13位タイにまで順位が下がってしまいました。
たった2打で、表彰圏外にまで落ちてしまうんですから、ルールの厳格さを痛感させられます。
笠りつ子の“誤所”プレーが話題に:ルールの盲点と学び
笠りつ子の“誤所”プレーが話題に:ルールの盲点と学びを深掘りしていきます。
①13番ホールでの誤所プレーの流れを整理
問題の13番ホールは、Vポイント×SMBCレディスの2日目のラウンド中に起こりました。
笠選手はセカンドショットでレッドペナルティーエリアにボールを打ち込んでしまい、規定に基づく救済を選択しました。
このとき、正しく最初にドロップされたボールは、ルール上「インプレー」と認められていたものの、本人はそれを誤って無効と判断。
2回目のドロップを行い、そこからプレーを再開してしまったのです。
この時点では誰も気づかなかったようですが、テレビ中継や録画を見ていた視聴者から「ん?今の…」と違和感が投稿され始めたんですね。
改めて見返すと、確かに微妙な判断が要求される場面でした。
プロでさえ迷うのなら、私たちアマチュアはもっと慎重に学ぶ必要がありますよね。
②1回目のドロップが「正解」だった理由
ゴルフ規則では、ペナルティーエリアからの救済でドロップを行った際、最初にドロップされたボールが所定のエリア内に止まれば、それが「インプレー」となります。
笠選手の場合、まさに1回目のドロップがこの条件に当てはまっていました。
にもかかわらず、そのボールを無効と判断し、再度ドロップを行ったことが問題となりました。
誤所からのプレーは、意図的でなくても罰がつきます。
だからこそ、「自分でOKだと思っていても、実はルール上NG」というケースは、怖いんですよね。
この一件は、「正しいルール知識の欠如」がいかに致命的かを物語っています。
ルールを過信せず、定期的な学習が大事だと痛感しました…ほんとに。
③なぜ2回目のドロップで違反と判定された?
多くの人が疑問に思ったのは、「なぜ2回目のドロップでプレーを続けただけで違反なのか?」という点。



これについて、ルール上の厳格さが鍵となります。
一度インプレーになったボールを無視して、別の位置から打つことは「誤所からのプレー」に該当するからです。
これがゴルフの“結果より過程を重視する”性質とも言える部分で、フェアであることを重視するルール設計が背景にあります。
つまり、「ちゃんとドロップされた場所から打ったか」が最も重視されるんですね。
スコアを縮めようとした意図がなかったとしても、ルール違反には変わりありません。



まさに“意図せぬ違反”の難しさ…。
④初心者がつまずきやすいドロップルールとは
今回の件はプロのミスですが、初心者にとっても他人事ではありません。
特にドロップ処置に関しては以下のような“あるあるミス”が多いです。
- 救済エリアの正確な範囲を把握していない
- ドロップ後、止まった位置の確認を怠る
- 最初のドロップが成功しているのに、再ドロップしてしまう
- 誤って膝より高い位置からドロップしてしまう
こうしたミスは日常的に起こり得るもので、ゴルフが「ルールを知っているかどうか」で大きく左右されるスポーツであることを再認識します。
もし不安なときは、遠慮せず同伴競技者やマーカーに聞くことが大切。
⑤誤所プレーが与えるスコアと評価への影響
笠選手の例からもわかるように、わずか2打のペナルティが大きな順位変動を生むことも。
| 状態 | スコア | 順位 |
|---|---|---|
| 違反前 | 通算1アンダー | 7位 |
| 違反後 | 通算1オーバー | 13位 |
ゴルフの世界では、たった1打の違いが賞金、世界ランキング、次戦の出場資格にも影響を及ぼします。
ルールを守ることは自分を守ること。
これ、ほんとに大事な教訓ですよね。
⑥今回の件で注目されたルール改正の必要性
SNS上では、「ルールが分かりづらい」「グレーゾーンが多すぎる」といった声も多く見られました。
確かに今回のようなケースでは、選手が「正しい処置をしていると思っていた」だけに、罰則が厳しく感じられた人もいるかもしれません。
それでも、現行ルールは「明確であること」を最優先として作られています。
もしルール自体を改善するなら、例えば以下のような工夫が考えられます。
- 現場で即確認できるルールガイドの整備
- 救済エリアの視覚的な表示の充実
- 初心者&プロ向けセミナーの定期開催
ルールは選手の敵ではなく、プレーを公平に保つための味方。
その理解を深めることが、ゴルファー全体のレベルアップにもつながると思います。
まとめ
視聴者の指摘はデマ?!笠りつ子のルール違反と誤所プレーとは?についてまとめました。
笠りつ子選手のルール違反は、ゴルフ界だけでなくSNS社会の新たな課題を浮き彫りにしました。
今回の件は、視聴者の指摘から始まり、動画が拡散され、正式な調査と裁定が下された極めて現代的な事例です。
違反はゴルフ規則14.7「誤所からのプレー」に該当し、2打罰によって最終順位が大きく変動。
この出来事をきっかけに、ルールの透明性と視聴者の役割、そして選手の精神的負担が改めて見直されています。
映像とSNSが新たな“審判”となる今、プレーとルールの両方への理解がますます求められる時代です。